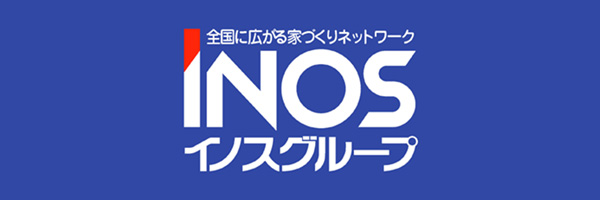先日、串本町にて上棟式を迎える事ができました。
4月とは思えない暑さの中、無事、棟が上がりました。
お家の守り神さまにお供えをし
家の四隅に 酒・塩・米を撒いてお清めをします。


屋根ができるまで 現場では 日影がほぼありません。
水分補給をこまめにしながら、手際よく進めていきます。
完成すると隠れてしまう部分。
しっかり丁寧に造り上げていきます。

上棟日。
おめでとうございます。
お客様のお気遣いに感謝いたします。
マメ知識 ~上棟式とは?~
工事の安全と完成、家内繁栄を祈る儀式です。

上棟式では「おかめさん」が飾られた御幣。
見た事ありませんか?
なぜ「おかめさん」が飾られているのか?
これには 理由があります。
鎌倉時代に腕のいい有名な棟梁がいました。
京都の千本釈迦堂の寺を建立するあたり、
棟梁は誤って4本の柱の1本を誤って短く切り落としてしまいます。
どうにもできない状況を救ってくれたのが
妻のおかめさんでした。
おかめさんの知恵のおかげで
どっしりと安定感をもった骨組みが出来上がります。

おかめさんは夫の棟梁の成功を祈り
「苦難が解けて工事が進展するならば私の命は惜しみません。」
と仏様に誓願をかけたため、約束通り、自らの命を絶ちました。
棟梁は 悲しみ、亡き妻のおかめをイメージした福面を飾り
妻の冥福と本堂の無事完成を永久に誓ったと伝えられています。
今でも 上棟式には おかめさんを付けた御幣は
棟梁を救った妻のおかめさんから由来したものです。
おかめさんには
工事の無事、女徳、良縁、子授け、夫婦円満などに功徳が大きいとされ、
工事が完成してからも家の守り神として棟木に奉ります。
昔からの習わしには想いや願いが込められた物語。
日本昔ばなしでも この話を見る事ができますよ。

小山麻紀
住宅資金アドバイザーの小山 麻紀です。主に資金計画、住宅ローン、土地探し、家のコト、住まいに関わる全般をお手伝いしています。
もみの木ハウス・わかやま LINE公式アカウント

もみの木ハウス協会の会員ブログ
「もみの木ハウス・鹿児島」のブログ
「もみの木ハウス・新潟」のブログ
「もみの木ハウス・大阪」のブログ
「もみの木ハウス・兵庫」のブログ
「もみの木ハウス・宮崎」のブログ
SNSやってます!
インスタグラム:公式ページ
Facebook:公式ページ
お願い
最近「もみの木」という事を売りにしたグッズ等を売り出しているお店があるようです。弊社が扱うもみの木とは関係はありませんのでお問い合わせは販売しているお店にお願いします。フォレストバンクのグッズはネットともみの木の家を建てる会社でしか販売いたしておりません。
正規商品は「のんき工房」までお問い合わせください!!
また、フォレストバンク製品に似せたもみの木の床等が出回っているようです。人工乾燥材のもみの木は不思議な力は無いかもしれません。正規なもみの木は「フォレストバンク」の製品を、「健康な住まいづくりの会」の正規会員よりご購入される事がよろしいかと思います。現在、9社ほど偽りのもみの木を扱う会社を確認しています。(平成28年9月に9社目を確認しました。社名を確認したい方は連絡いただければお知らせいたします)
もみの木が「フォレストバンク」製品かを今一度お確かめください。悲しいお問い合わせが来ております。正規品は「健康な住まいづくりの会」の正規会員よりご購入された方が安心です。騙されない事を祈りますが、欲が騙します。お気を付けください!!
ご注意
フォレストバンクのフォレストキングなどの商品は普通の商材ではありません。お問い合わせは知り得た人、もしくは会社にお願いいたします。それ以外にお問い合わせをする場合、販売できなくなる可能性が有ります。
また、弊社でもみの木の家をご検討される場合、事情によりお断りする場合がございます。もみの木は他でも入手可能です。そちらでご検討ください。お願いいたします。
家づくり情報サイト「コダテル・和歌山」で当社が紹介されました。